
講談社の女性誌「with」が3月28日発売の5月号をもって事実上の休刊をするという。ウェブによる情報は発信していくというが、紙媒体に関しては廃刊である。この「休刊」という言葉に一般の方からは、「?」の声をよく聞く。本来は復刊含みである場合にそう書く。有志が看板(雑誌商標)を従来の発行会社から買って復刊したりするケースがごくたまにある。しかし「廃刊」という言葉がちょっときつい印象なので武士の情けで「休刊」という言葉を使ったりするケースがほとんだ。出版社が止めた雑誌を再び発行するなどということはまずない。
「with」は、ファッション誌というよりも女性情報誌とか総合女性誌というカテゴリーに入るが、ピークは平均45万3000部(2005年)だった発行(印刷)部数が昨年は8万9000部まで落ち込んだという。16年間でこれだけ急減するのだから、今の女性からは必要とされていないということなのだろう。
講談社の女性誌の主だった休刊をまとめてみると:
・STYLE(2001年9月~2008年11月号)
・Grazia(1996年3月~2013年8月号休刊)
・GLAMOROUS(2005年4月~2013年8月号休刊)
の3誌が主な存在だが、創刊後にすぐ廃刊になったファッション誌「gli」があった。簡単に言うと、どうもファッションという分野が得意ではないようなのだ。「VOGUE」などのハイファッションでは、海外(提携)誌には勝てないし、「みだしなみ」レベルのローファッションでは付録付きの宝島社軍団のところまで下りていけない。なんとも中途半端なミドル・ファッションで戦っているということが苦戦を招いているのだろうか。
漫画に優秀な人材が行ってしまっているという指摘も当たっているとは思えない。漫画の編集者の仕事というのは有能な漫画家、ヒット作を生める漫画家の発掘に尽きるわけで、売れる雑誌を作るクリエイティブな企画力とは全く別の才能が求められる。大手出版社の雑誌編集者には、売れる雑誌を作るクリエイティブな力が足りないということなのか。これは講談社に限ったことではなくて、大手出版社全般に言えることだろうか。15年ほど前だったか、講談社の10人ほどの新入社員が全員東大生だったのを思い出したのだが、なんとなくそのあたりに遠因があるような気がするのだが。成績がいい頭のイイ奴ばっかりだと、売れる雑誌は作れないような気がするが。
先日NHK総合テレビの「プロフェッショナル 仕事の流儀」を見ていたら、ハルメク出版の月刊「ハルメク」の山岡朝子編集長(47歳)を取り上げていた。書店では買えない郵送による定期購読誌で50歳以上の女性を対象にした月刊誌である。愚妻宛てに毎月届くのでその存在は知ってはいたが、その雑誌が定期購読者38万人で5年連続50歳以上対象の雑誌日本一を誇っているとは夢にも思わなかった。失礼ながらダサい雑誌である。「Marisol」や「eclat」(集英社)などが遅まきながら「ハルメク」のマーケットに殴り込みをかけたのだが、「Marisol」は昨年休刊。「ハルメク」のダサイ感じまではどうしても降りていけない。どうも眼高手低で泥臭くなれないのだ。
そうかと思えばファッション誌販売部数11年連続トップシェアを誇る宝島社の「付録付きならウェブにも勝てる」というコロンブスの卵的なその泥臭さにもやはりやられてしまった。
話がそれてしまったが、講談社、集英社、小学館は漫画とライツビジネス、ウェブビジネス、不動産収入で史上最高決算が続いている。この好調な時期に大ナタをふるって不採算事業をやめてしまおうという戦略なのだろう。これはよく理解できる。もう出版社という感じではないのだ。
要するにほとんどが広告狙いの欲望喚起装置にすぎない雑誌には、寿命があるのは当然なのだ。それにしても急ピッチで進む休刊ラッシュには呆れるばかりである。コロナ禍をいいことに不採算雑誌の整理が今年も続きそうだ。編集ページでも広告出稿ブランドにはいちいちお伺いを立てるようなことを続けていたら読者は離れて行くに決まっている。ある意味毅然としたジャーナリズムや純然たる好奇心が雑誌からなくなったらオシマイなのである。
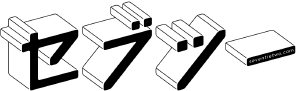
![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)