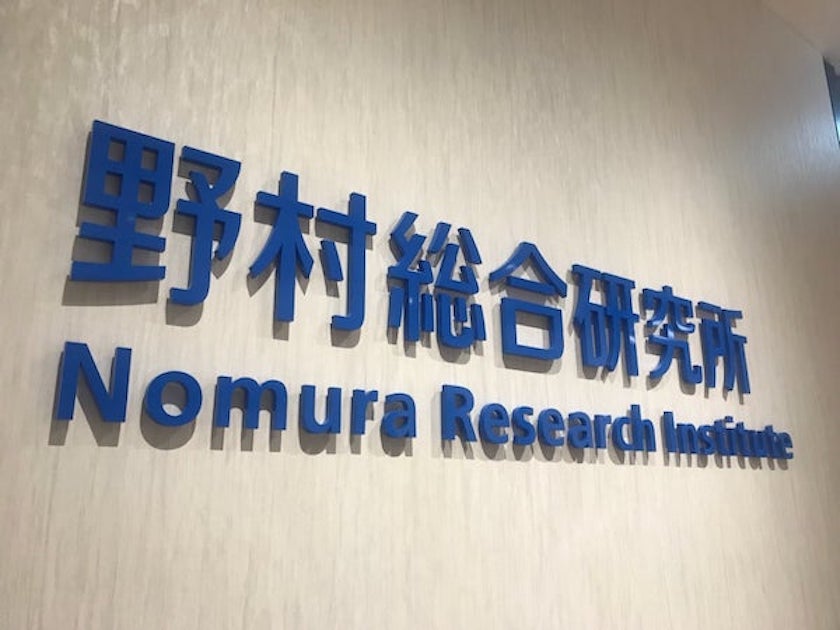
野村総合研究所は1997年以来、3年に1回全国の15〜79歳の男女1万人を対象にして、訪問留置法(訪問してアンケート用紙を置いて数日後回収)で生活像、生活価値観、消費実態を尋ねる「生活者1万人アンケート調査」を行なっている。第9回目の今回は2021年8月に行われたが、11月末にその調査結果が発表になった。その中からいくつかのポイントをダイジェストした。
1.「今年から来年にかけての景気の見通し」については、今回「悪くなる」という回答が40%で、今までの9回のうち最高だった。ちなみにこの「悪くなる」という回答は、2015年22%→2018年19%と減少していたので、今回のコロナ禍で一気に過去最悪の数字になった。8月という調査時期が、新型コロナデルタ株が急増して、日本全国で1日の新規感染者が2万5992人(8月20日)の最高人数を記録するなど感染拡大の山場にあたっていたことが「異例の高率」の原因になっているとは思う。感染拡大が収束の兆しを見せている12月ならば結果はかなり違っているような気はするが、それにしても高率ではある。野村総合研究所では7月にも全国1万8800人を対象にした大規模インターネット調査を実施して、「コロナが収束してもリベンジ消費は限定的」として、50%以上が「消費はコロナ禍以前の水準には戻らないだろう」という回答だったことを発表している。いずれも調査時期が悪すぎたように思える。
2.生活満足度に関しては「満足している」と「まあ満足」の合計が2021年調査では78%と調査開始以来の最高値をマーク。
1997年以降、その数字は、72→71→71→72→68→73→76→76→78の推移だ。自粛による時間的な余裕が生まれたこと、生活でのデジタル化の浸透により、生活者はウィズ・コロナの新しい生活様式に満足しているという結果が出ていると結論付けている。これは今回の調査で最大の驚きと言っていいのではないのだろう。要するに生活者は、コロナ禍前は、通勤なども含め所属企業に時間をあまりにも取られていたということが明らかになったのではないだろうか。
3.テレワーク浸透で就業価値観が多様化
さて、今回の8月の1万人調査でもうひとつ注目されるのは、テレワークの浸透などにより就業価値観の多様化が起こっているという調査結果だ。会社の発展や出世のために尽くすよりも、ワークライフバランスへの意識が高まっており、近年では副業への意向が高まっていると結論付けている。実際にテレワーク業務を実践できた人は就労者全体ではわずか22%と意外に低い。管理職・事務職・専門職で高く、正社員や従業員数の多い企業ほど高かった。ワークライフバランスへの意識の高まりと結論付けているが、簡単に言って、プライベートライフを重視するようになったということ。これはテレワークした人ほど割合が高く、テレワークで家族と一緒に過ごす時間が増えたことやプライベートライフの充実で、今までの会社中心の生活に対する「反省」が生まれたようだ。
4.デジタルレジャーが伸長し、ショッピングもインターネットで完結
これまで拡大してきた「外食・グルメ・食べ歩き」や「映画・演劇・美術鑑賞」、「カラオケ」などの「街レジャー」は減少し、代わりに動画配信サービスの利用拡大を背景に「ビデオ、DVD鑑賞」などのデジタルレジャーが伸長。さらに消費に関しては「実際に店舗に行かずに、インターネットだけで商品を買うことがある」のは、2012年の28%から2021年にはなんと49%まで伸長。
5.「プレミアム消費」スタイルが増加
野村総合研究所では消費傾向について「利便性消費」「プレミアム消費」「安さ納得消費」「徹底探索消費」の4つの指標を設定しているが、2000年以降のその推移は:
・利便性消費 37→35→36→34→37→44→44→41
・プレミアム消費 13→18→19→20→22→22→22→24
・安さ納得消費 40→34→32→31→27→24→24→24
・徹底探索消費 10→13→13→14→14→10→10→11
強いてあげれば、プレミアム消費の伸長か。これもコロナ禍による影響が大きいようだ。
6.中高年層におけるスマートフォン保有が伸長。消費の情報源はネット
スマートフォンの個人保有率は、生活者全体では、2012年23%、2015年52%、2018年71%、そして2021年84%と伸長。特に50代以上の中高年層で伸長が著しく、70代では男性57%、女性54%という水準。消費の際の情報源は、「TVのCM」および「ラジオ、新聞、雑誌の広告」は2012年以降減少を続け、「ネット上の売れ筋情報」「評価サイトやブログ」といったネット情報の参照割合が伸びている。
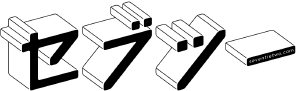
![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)