「コム デ ギャルソン・オム プリュス」2022-23秋冬 「ギャルソン流 チャップリン」の希望と優しさ

「コム デ ギャルソン・オム プリュス(COMME des GARÇONS HOMME PLUS)」の2022-23秋冬コレクションショーが南青山のコム デ ギャルソン社本社ビルで1月17日に行われた。私は実際には見ていないが、その収録ビデオを見ると、意外にも一種の「希望」や「優しさ」をそこに感じて驚いた。社会や時代に対する怒り、怨念、不安、絶望などが支配し続けて来た川久保玲の創作姿勢の中で、「オム プリュス」に関しては昨シーズンあたりから、そうした「希望」というものが強く感じられるようになったのは、やはり、今年80歳になるデザイナーの晩年の様式の表れと言っていいのだろうか。
なんとも言えぬ「優しさ」が、穏やかなフォルムと色使いに感じられるのだ。今コレクションのテーマは「ノマド(=遊牧民、放浪者)」だという。
ショーの後に配られた、川久保玲によるコレクションノートには、「今知りたいと思えば情報はいくらでも手に入る。Internetにより何処へでも行くことができる。経験したことになる。しかしそれでも私は満足できない。属さない。群れない。真に自由に自分自身で生きるノマドに憧れる。羨ましい」と記されている。
全てのルックに恐ろしく背の高い様々な山高帽がコーディネイトされている。放浪者と山高帽、これにチョビ髪を付けてステッキをもたせて厚底の革靴を履かせてみて欲しい。何かを連想しないだろうか。まさにこれはサイレント時代のチャールズ・チャップリンの世界ではないか。私にはそう感じられてならないのだ。
チャップリンのサイレント時代の最後の映画、つまり山高帽にダブダブの黒のスーツ姿の放浪者チャップリンが見られる最後の映画が「モダン・タイムス」(1936年)だ。そのラストシーンは、いつもラストシーンでは一人だったチャップリンが、珍しく浮浪少女(ポーレット・ゴダード。チャップリンと事実婚中)と二人ではるかに続く一本道を歩き去っていく後ろ姿になっている。哀愁を含みつつも希望が感じられる一種のハッピーエンドだ、もちろん「コム デ ギャルソン」に「哀愁」はないし、「笑い」もない。しかし、同様に自由を求めたあてもない歩みは続けられる。
「コム デ ギャルソン」には珍しい「希望」と「優しさ」を感じさせるのは、そうした映画の残像が私の脳裏に浮かんだこともあるかもしれない。
いずれにしても、晩年の様式に入ったと思われる川久保玲が、このコロナ禍の時代に、あるいはコロナ禍が去った今後に、どんな作品を発表していくのか、興味は尽きない。
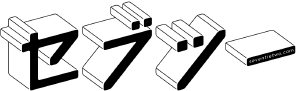
![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)