
集英社の雑誌「セブンティーン(SEVENTEEN)」と「マリソル(MARISOL)」が定期刊行を終了するのは、既にこの「SEVENTIE TWO」でも既報されている。「廃刊」とは書かずに、「休刊」と書くのは同じ出版業界に生きる者としての「武士の情(なさけ)」なのであるが、この「定期刊行を終了」という書き方はなかなか「斬新」ではある。
「マリソル」は同社の雑誌「エクラ(eclat)」との差別化が難しかったのではないだろうか。「マリソル」は2007年3月の創刊でターゲットは30代後半〜40代のいわゆる「アラフォー」である。これに対して「エクラ」の創刊は「マリソル」の半年後の2007年9月でターゲットは40代後半〜50代でいわゆる「アラフィフ」である。振り返ってみれば、同じ年に「アラフォー」雑誌と「アラフィフ」雑誌をスタートしていたのである。創刊当時も「どっちが『マリソル』でどっちが『エクラ』か当ててみて?」クイズが出版業界で流行っていたぐらいであるから、これはどう考えても「無理筋」である。今どき40代女性と50代女性に大きな違いがあるのだろうか。これは年代でライフステージを無理矢理に区切ってしまうマーケティングの失敗例と言えるのではないだろうか。逆に言えば、こういう「無理筋」を実行するほどに大手出版社は雑誌に対して自信があったということなのだろう。
思い起こせば、2008年9月15日のリーマンショック、2008年9月8日の「H&M」日本上陸(銀座旗艦店オープン)というファッション誌&ライフスタイル誌にとっての「ダブル・ショック」が1年後に待っていた時期で、雑誌にとってはある意味では燃え盛る最後の炎のような時期だったのかもしれない。もしやと思って調べてみたら、集英社の親会社と言っていい小学館でもこの2007年3月7日に「キャンキャン(CanCam)」のお姉さん雑誌を謳った「姉キャン(AneCan)」が創刊されていたのである。80万部を突破して向かうところ敵なし状態だった「キャンキャン」の読者層の年齢が上がって来たのでそのお姉さん版を創刊したのだ。「両誌合わせて少なくとも80万部はキープできるはずで広告収入は1.5倍になるはず」というのが「姉キャン」創刊時の目論見であった、前述したようにその翌年の「ダブル・ショック」までは読めなかったようだ。「姉キャン」は9年後の2016年11月7日発売の12月号を最後に休刊した。また、「キャンキャン」の凋落も激しく現在の印刷証明付き発行部数は8万9,000部(日本雑誌協会調べ、2019年1月〜3月平均)だ。懐かしい山田優、押切もえ、海老原友里の3枚看板時代の実に9分の1である。
ことほど左様に今回の「マリソル」の定期刊行終了はなかなかに教訓的ではある。まあ「一寸先は闇」と言うべきか、あるいは「調子に乗るとロクなことはない」と言うべきか。
今回集英社が定期刊行終了したもう一つの雑誌「セブンティーン」は、1968年6月の創刊である。週刊、月2回刊を経て最後は月刊誌になっていたが、ライバル誌の「プチセブン(Petit Seven)」(小学館)が2002年3月に休刊後は急速に部数を伸ばしていたが、これも創刊40周年を機に2008年10月号から表記も「SEVENTEEN」に変更し月刊化したあたりから低迷が始まったようだ。前述の「ダブル・ショック」をモロにかぶったようだ。最近はギャルたちの活字離れは急加速で進んでおり遂に53年の歴史に終止符を打つことになった。
この「セブンティーン」は実はライセンス誌でライセンス先は1944年創刊の「SEVENTEEN」で発行元はハースト ・コーポレーションである。ハースト の日本法人はハースト 婦人画報社である。今回の「定期刊行終了」には、このライセンス契約がどう関係しているかは定かではない。ライセンス料が負担だとかハースト婦人画報社が日本で集英社に代わって発行することにしたということもなさそうである。
今回の集英社の「マリソル」「セブンティーン」の定期刊行終了は、言うまでもなく集英社の経営が厳しいためではない。既報しているように、昨年2020年5月期の同社の2020年5月期決算は売上高1529億400万円(前年比14.7%増)、当期純利益は209億4000万円(同112.0%増)と前年度の2倍以上の史上最高決算だった。デジタル、漫画、ライツビジネス、不動産の事業が完全に軌道に乗って当期利益で98億円を叩き出して画期的と言われた2019年5月期の倍以上をマークしたのだから恐れいる。この機に社内の懸案を片付けておこうという方針なのだろう。「マリソル」「セブンティーン」の「定期刊行終了」もその一環であろう。儲かっているから不採算雑誌も残してみようなどとは決して考えないのである。
もう「出版文化」の旗を掲げて雑誌を育てたり、社員を「出版人」として育てたりするというような出版社経営は時代遅れだということなのだろう。出版社という呼び名もすでにふさわしくないような気もしてくる。
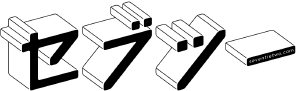


![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)