
坂本龍一のドキュメンタリー映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4Kレストア版の劇場公開を記念したトークイベントが2月8日、坂本龍一が音響監修を手がけた「109シネマズプレミアム新宿」で開催され、岡村靖幸と藤原ヒロシが登壇した。チケットは発売と同時に完売するなど注目度の高いイベントとなり、会場には音楽ファンや映画ファンが詰めかけた。LINEでも交流があるという2人は、日頃から本作について語り合っているといい、上映後のトークでは映画の魅力や当時の東京カルチャー、音楽制作の現場、坂本龍一の人物像について幅広く語り合った。
岡村はかつてDVD版で本作を鑑賞しており、「すごく貴重な映像ですよね。坂本さんの『音楽図鑑』というアルバムのレコーディング風景や、当時の東京の風景もあって。今だったらこれオッケーが出るのかな、というような映像や、スタジオでご飯を食べているシーンなど、いろんな映像が入っていて。すごく生々しくて、貴重な映像が満載で。当時から面白いと思っていました」と当時の印象を振り返った。映画には1980年代前半の東京の街並みやカルチャーが色濃く残されており、秋葉原や新宿アルタ前の映像、竹の子族やロックンロール族など、時代の熱気が詰め込まれている点にも話題が及んだ。
一方、今回が初鑑賞だった藤原は「僕はすごく当時のことを思い出しました。僕は坂本さんとは世代が離れているんですが、82年から東京にいた。坂本さんとお仕事を一緒にしたことはなかったんですが、同じ空間にいることが結構あったんです。映画には、当時の音楽の作り方が映し出されていて。特に(シンセサイザーの)フェアライトとか、そういうものが出てきて懐かしかったですね」と語り、自身のDJ時代を振り返った。また坂本との接点についても、クラブやニューヨークのそば店で顔を合わせていたエピソードを紹介し、今思えばもっと音楽の話を聞いておけばよかったと率直な思いを明かした。
トークの中で2人が特に盛り上がったのが、スタジオ機材の存在だった。映画に登場する世界初のサンプリング・マシン「フェアライト(Fairlight CMI)」は当時1200万〜1400万円とも言われる超高額機材で、音楽制作の歴史を変えた象徴的存在だという。藤原は「これがちゃんと映像に残っているというのはすごいですよね」と語り、自身が初めてフェアライトを見た時の衝撃や、その後720万円のサンプラーを借りてYMOのリミックスを制作した経験を振り返った。さらに映画に登場するスタジオの食事シーンについて、「1400万のフェアライトの前にある卓の上で、出前でとった食事を食べていましたもんね。普通食べないですよ」と笑いながら話すと、岡村も「あの卓だって何千万としますからね」と応じ、会場は大きな笑いに包まれた。
また当時、サンプリング技術の登場により「オーケストラが不要になるのではないか」「生演奏は消えるのではないか」といった議論が巻き起こったことにも話題が及び、藤原は「音楽業界の中でみんなが話題にしているという意味では、今のAIと近いなと思うんです」と指摘。岡村も強く共感し、坂本が常に最先端のテクノロジーに目を向けながらも、エラーやノイズといった不完全さに価値を見出していた点に言及し、もし現代に生きていたらAIとどう向き合っていたのか想像すると興味深いと語った。藤原も自身が音楽理論を知らないままパンクやヒップホップに出会い現在に至った経験を語り、アカデミックな背景を持ちながらもノイズや綻びに向き合った坂本の姿勢の特異性を称えた。
さらに坂本の音楽性について、岡村は予想と裏切りのバランスが作品を生むという言葉に共感を示し、その絶妙な構成力が美しいメロディと前衛性を同時に成立させていたと分析。物作りに関わる人間なら誰もが共感できる考え方だと語った。また本作の演出について岡村は「ドキュメンタリーだとよくコメントが入ったり、ナレーションが入ったりと、説明が入るものですが、この映画はフランス映画っぽいですよね。ロードムービーみたいな、沈黙の部分もたくさんあって。間の取り方とかも普通じゃない感じで、ゆったりとして見ることができた。まさに外国の方が撮った感じがすごくしました」と印象を述べ、藤原も外国人監督ならではの視点が当時の東京の魅力を新たに浮かび上がらせていると評価した。
坂本の人物像について岡村は「僕は一貫して坂本さんに関して思うのは“ルックスがいい”ということ」と語り、音楽性だけでなく存在感やスター性が時代を象徴していたと分析。実験性とポップ性、知性とユーモアを兼ね備えた“トリックスター”的存在だったと振り返った。最後に作品の見どころについて岡村は「映画では大事な言葉をいろいろと言っているんですが、1回目は見逃してしまうこともあります。でも何回か見ていくうちに、こんなこと言っていたんだと」と再鑑賞の魅力を強調し、藤原も坂本の言葉の中に今につながるヒントが隠されていると来場者に呼びかけた。1980年代東京の空気と坂本龍一の創作の核心を捉えた本作の価値が、2人の言葉を通じて改めて浮き彫りとなった。
『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』は1985年に公開され、「幻のドキュメンタリー」として語り継がれてきた作品だ。坂本龍一をはじめ、矢野顕子、細野晴臣、高橋幸宏らが出演し、監督はエリザベス・レナードが務めた。レナード監督は、大島渚監督作『戦場のメリークリスマス』で坂本龍一の存在に魅了されたことをきっかけに、本作の制作に着手したという。
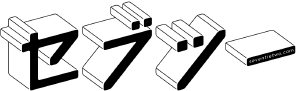














![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)