
「#ワークマン女子」が銀座に4月28日旗艦店をオープンするというニュースが2月22日に発表された。まあ字面が踊っているだけで、きちんとした記事がほとんどないのが嘆かわしい。
場所は、銀座5丁目7番地10のイグジットメルサ。銀座中央通りに面してはいるがこのイグジットメルサは失礼ながらB級ファッションビルである。しかも、その5階である。では、以前は何が入居していたかと言うと、「ラオックス銀座EXITMELSA店」が昨年9月30日まで営業していたフロアである(これに言及したのはFASHIONSNAP.COMのみ)。来日した中国人狙いの免税店だったのだろうが、最近のコロナ蔓延情勢では閉店もやむなしということなのだろう。また売り場面積のことを書いている記事も少なく、繊研新聞によれば約300㎡(90坪)。同新聞によれば、売り上げに対する家賃比率は、3%が基準だが、銀座店は4%の試算で1年目から大幅な黒字になり同ブランドの売り上げトップ店になるという。またこれも記載のない記事が多いが、初年度売り上げ目標は6億~7億円だという。仮に初年度売り上げが6億円だとすれば、1カ月あたり5000万円。月当たりのトータル家賃はその4%なら200万円。月坪家賃(1坪あたりの1カ月の家賃)は2万2222円になる。B級ファッションビルの5階と言っても、天下の銀座で月坪家賃が2万2222円ということはあり得ないと思うがどうなのだろう。いくらB級ファッションビルの5階でも月坪家賃は5万円はするはずで、ということは発表の初年度の売り上げ目標はマスコミ向けで、社内的には月1億円、年間12億円を目論んでいるということなのだろうか。それなら納得できる。
それはともかく、ワークマンの小濱英之社長によれば、「日本人の大半が『ユニクロ』には行ったことがあるが、『ワークマン』に来たことのない人はたくさんいる。銀座への出店で発信力を強め、客層のさらなる拡張に挑む」と念願の銀座進出を決定(繊研新聞より)という。認知度を上げたいならば、家賃は高くとも1階部分への出店を考えればよさそうなものだが、基本はウェブ注文・店頭受け取りだから、5階で十分ということなのだろう。なかなかしっかりしている企業だ。
繊研新聞の記事で注目されるのは、ワークマンは、実はベイシアグループ(発祥は群馬県伊勢崎市の衣料品専門店「いせや」)の一員だということ。このベイシアグループは他にホームセンター業界ナンバーワンのカインズ(最近東急ハンズ買収で話題になった)や家電量販店のベイシア電器、仏壇の清閑堂などを擁しており、2020年10月にグループ総売上高1兆円を達成している。グループ内ではカインズ(2021年2月期売上高4854億円)が突出しているが、2021年3月期売上高1058億円で1000億円企業になったワークマンがそれに継ぐ存在だ。今回の「#ワークマン女子」の出店計画でもカインズなど郊外SC敷地内で路面型11店の出店を来期予定しており、2023年3月末にトータルで27店を予定(2022年3月末では12店)している。2030年には「#ワークマン女子」で400店体制になるという遠大な計画も発表している。その中には、全国の百貨店も対象になるというから、まさにカテゴリーキラー。もちろん作業服ではないが、まあ作業服のようなワークスーツやカジュアルウェアが百貨店で売られる時代が来たということだろう。
さて、#ワークマン女子の銀座店での成功確率だが、ワークマンが発表しているマスコミ向け初年度6億~7億は今の勢いならまずクリアは間違いないだろう。前述したように狙っている本当の初年度目標はその倍の月1億円、年間12億円だと思うが、ウェブ注文が中心ならこれもクリアするのではないだろう。問題はその後ということだ。例えば、銀座中央通りに面した銀座7丁目に単独路面店を2008年9月13日にオープンした「H&M」は、それから10年経った2018年7月16日に閉店してしまった。世界で約2兆5000億円を売るファストファッション業界第2位の「H&M」にしても、10年契約を更新できなかったのである。もちろん赤字だから閉店したのである。そういうビジネスの難しさが銀座にはある。果たして「#ワークマン女子」あるいは「ワークマンプラス」が、一過性のブームでなはく日本のアパレル市場の雄として定着できるのかどうか、第2の「ユニクロ」として定着できるのかどうか大いに注目したいと思う。
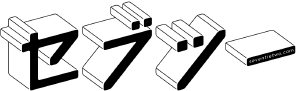






![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)