
3月22日に、南青山のコム デ ギャルソン本社で2021−22年秋冬の「コム デ ギャルソン(Comme des Garçons)」のフロアショーが80人ほどのジャーナリスト、取引先を招いて行われた。40年ぶりに東京で開催された昨年9月のショーと同様で、コム デ ギャルソン社としては開催地が東京であるだけのパリコレのつもりで開催しているのであろう。海外からのジャーナリストの来場はなく、海外媒体については委嘱された東京在住のライターが来場していたという。オンライン配信はしているが、世界のファッションシーンから取り残されてしまうのではないかというような危機感はあまり感じられない。我が道を往くということか。
私は限られた80人ほどのジャーナリストなどに選ばれているわけでもないから、10分ほどのショーの動画とその後本社で行われた展示会を見ただけである。ショーの後にバックステージでデザイナーの川久保玲同社社長が今回のファッションショーについて語り、質疑応答もあったという。紙、webも含めて、このファッションショーについて書かれたレポートを読んでみたが、レジメが配られたのか、ほとんど同じことが書いてある。

「音や色から離れたい」という現在の心境を表現しすべて白と黒でまとめられた20体のショーは「モノクロームの風景(Landscape of shadow)」と題されている。今年3月のショーは「不協和音」がテーマのエネルギッシュな少々騒々しい内容だったから、まさに一転した内容である。なぜそんな大変化がわずか半年で起こったのか。ジャーナリストの皆さんには是非尋ねてほしかった。たとえ答えはわかっていたとしてもである。たぶん川久保玲はこう答えたはずだ。「気分がそうだったから」。しかしどう見ても、白と黒が織りなす異形の世界は尋常ではない。精神が病む一歩手前のところまでいっている。

ジャーナリストならもっと追求してもらいたいものである。ちゃんと答えてくれないなら、そこは想像力で補うしかないのではないか。1942年10月11日生まれの78歳のデザイナーがこのコロナ禍でどんなことを思ったのか。それを語ってくれないのならば、ジャーナリストは「作品」が語っている言葉に耳を傾けるべきなのである。要するに、ただのレポーターばかりなのであろう。
感染者数や死者数の情報が氾濫するコロナ禍の世相に嫌気がさしただけにも思えない。78歳のデザイナーには何かあったのではないだろうか。肉親の死、友人の死、同志の死、自身の病などが。広報室を通じてメールで尋ねたが「関係はありません」。いずれにしてもそうした心境をファッションという「芸術」に昇華されずらい世界で堂々とやってしまう。スモークを炊くだけの簡素な演出と書かれているが、20体のルック同様に突き刺さってくるのが音楽だ。White Stains(ホワイトステインズ。「白い染み」という意味か)というベルギーの音楽集団のシンセサイザーによるミニマルミュージック風の「音楽」である。この集団のフェイスブックによると「Pale desires」(2020)というアルバムからほとんど選曲されているようだ。放心しているようだがそこでは「怒り」にならないような「恨み」が低く呻いている。もう「現世」ではないあの世で奏でられている「音楽」にもならないような「音」である。
この音が、白と黒の「コム デ ギャルソン」のファッションというよりはオブジェとシンクロして、この世ならぬ静謐の世界を現出させる。そこに漂うのは一種のかぐわしい死臭であり、感じられるのは底知れない「疲労感」である。「コム デ ギャルソン」はこんな世界についに辿り着いてしまった。これは川久保玲が描く「彼岸の風景」なのかもしれない。ちょっと空恐ろしくなってくる。私が選曲家なら、グスタフ・マーラーの最後の交響曲第9番終楽章アダージョを選んだと思うが、これですら少々「色」があって感傷的なのかもしれない。一切の感傷は厳しく排除されているのだ。
それは私には78歳のデザイナーの「遺言」のように思える。これからの「コム デ ギャルソン」のショーは心して観るべきものである。

写真はコム デ ギャルソン社より提供
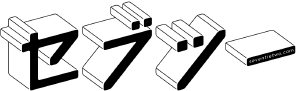







![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)