
メルカリがスキマバイト事業「メルカリ ハロ」を2025年12月18日で終了する。サービス開始からわずか1年9カ月だった。登録者数は1200万人を超え、一時は業界最大手「タイミー」を上回っていた。それでも、メルカリは撤退を決断したんだ。
公式発表では「市場環境や利用状況を踏まえた総合的判断」と淡々と説明されたが、「履歴書不要・即日勤務・即日入金」という手軽さは、生活のスキマを支える新しい働き方として支持を得ていたので、SNS上ではザワザワしていたね。
■なぜ撤退したのか?
メディアによると、「メルカリ ハロ」の登録者数は1200万人に達していたが、2024年の就業実績は約94万人。タイミーの約1805万人と比べると、約19倍の差がある。つまり、「登録」はできても「稼働」までは進まなかったんだよ。
更に2025年4月から、企業向け有料化を導入したことで採算悪化が進み、システム運用・採用・広告コストを差し引くと、赤字幅は10〜15億円規模。グループ営業利益(約320億円)の3〜4%に影響する「非効率部門」になっていたんだ。
■では、タイミーとの差はどこにあったのか?
タイミーは営業人員600人規模・全国39万拠点を持ち、店舗や企業の運営現場に深く入り込んだ。一方の「メルカリ ハロ」はプラットフォーム志向が強く、アプリ上で完結する仕組みを重視。現場のマネージャーが使いこなすまで、スムーズにいかなかった。
■株主・アクティビストにとって、今回の撤退をどう見る?
OASIS Japan(3.9%保有)など海外ファンドは、以前から「非コア事業の整理」「ROE改善」を提言していた。今回の撤退はその要望への直接的な回答だ。実際、IR資料では「配当より自社株買いを優先」と明記されており、非収益部門の整理で、営業利益率+0.5pt、ROE+1ptの改善が見込まれる。
OASISにとって「メルカリ ハロ」撤退は「勝利」に見えるが、同時にメルカリ社の「次の一手」を見ている。撤退後の資本配分──「メルペイ」「メルロジ」「越境EC」のいずれに再投資するのか?短期の削減を評価しながらも、次の成長ストーリーを試している段階だ。株主が納得するのは、やはり「やめた理由」ではなく「どこに集中するか」の説明だよな。
■では、もう一度メルカリの本業を再確認
今回の撤退で、逆にメルカリの本業の輪郭ははっきりした。それは「モノ・お金・物流の循環をデザインすること」だ。フリマアプリでモノを動かし、メルペイでお金を流し、メルロジで届ける。この三つの循環をいかに効率よく回すかが、企業の中核になっている。「自分たちの本業は何か?」を経営陣も株主も再確認できたのではないか?
■株価の評価は?
「メルカリ ハロ」撤退で「非コア整理」は完了。残るは「Fintechでの収益化」と「越境物流の拡大」。それが見え始める2026年3月決算期を待つなら、巳之助が考える購買レンジは 2,200〜2,300円だなあ。
巳之助は「やめる勇気」が、「続ける力」に変わる瞬間を見た。
プロフィール:いづも巳之助
プライム上場企業元役員として、マーケ、デジタル事業、株式担当などを歴任。現在は、中小企業の営業部門取締役。15年前からムリをしない、のんびりとした分散投資を手がけ、保有株式30銘柄で、評価額約1億円。主に生活関連の流通株を得意とする。たまに神社仏閣への祈祷、占い、風水など神頼み!の方法で、保有株高騰を願うフツー感覚の個人投資家。
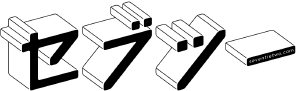


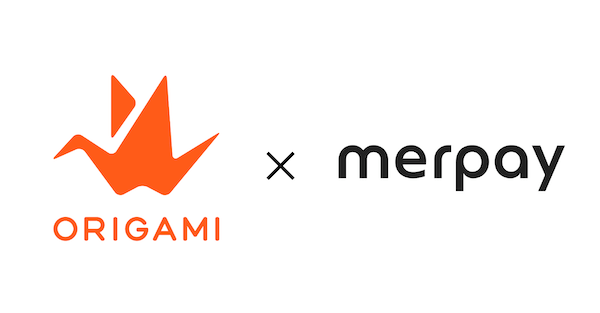


![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)