
アパレル業界で企業の破産や民事再生法の申請が相次いでいる。2025年夏にかけて、全国各地で中堅規模のファッション関連会社が相次いで経営破綻に追い込まれた。背景には、消費者の購買行動の変化や物価高騰によるコスト増加、そしてEコマースやSNS発の新ブランドとの競争激化などがあるとみられる。
8月20日には、英ブランド「ポール・スミス(Paul Smith)」のバッグや革小物などを手掛けてきたスタイル(本社:東京都墨田区、代表:金子豊)が東京地裁へ破産を申請した。負債総額は約21億5000万円にのぼる。スタイルはライセンス事業を中心に展開し、かつては百貨店や専門店を通じて広く販売網を築いたが、近年は消費者ニーズの変化に対応しきれず、売上の低迷が続いていた。
同日、宮城県仙台市に本社を置くエミル(代表:佐々木浩)も自己破産を申請。カジュアルウェアを展開してきたが、負債総額は約12億円。地方都市を中心に事業を展開していたが、EC市場の拡大や低価格ファッションとの競争で苦戦を強いられた。
さらに18日には、大阪市に拠点を構える子ども服メーカーのジェニイ(代表:平原亮太)が自己破産を申請。負債総額は約15億円に達した。ジェニイはガールズブランドを中心に展開し、若い母親層に人気を集めた時期もあったが、少子化の影響に加え、Z世代をターゲットにする新興ブランドの台頭も打撃となった。
地方企業にも波及している。福島県喜多方市のカジュアルウェアメーカー、R1000(代表:金子一弘)は自主再建を断念し、7月29日に民事再生法を申請。負債総額は約34億3000万円に達した。さらに5月27日には、シューズの小売「ゼットクラフト(Z-CRAFT)」やキャンプ用品「ピースパーク(PEACE PARK)」を展開するロイヤル(本社:名古屋市、代表:中根智大)が東京地裁に民事再生法の適用を申請した。負債総額は約93億1800万円。
こうした一連の破綻は、アパレル業界が直面する構造的な課題を浮き彫りにしている。第一に、消費者の購買行動の変化だ。かつては百貨店やショッピングモールでの購買が主流だったが、現在はSNSでトレンドを知り、即座にECで購入するスタイルが一般化した。そのスピード感に対応できないブランドは存在感を失いやすい。
第二に、コスト上昇の圧力だ。円安や原材料費の高騰に加え、物流や人件費も上昇を続けており、特に中小企業にとっては致命的な打撃となっている。海外生産への依存度が高い企業ほど為替リスクを受けやすく、コストマネジメントに対応できなければ、安定した収益モデルを構築するのが難しくなっている。
第三に、新興ブランドの台頭だ。SNSを起点とするD2Cブランドは、広告宣伝費を抑えながら若い世代にリーチできる強みを持つ。一方、従来の卸売型モデルを維持する企業は在庫リスクや販売チャネルの制約に苦しみやすい。
また、コロナ禍を契機にデジタルシフトが加速したことで、旧来型のビジネスモデルを続ける企業は再編や淘汰の波に直面している状況もうかがえる。今回の一連の破綻は、中小規模のアパレル企業にとって「経営環境の急激な変化」にいかに対応できるかが生き残りの分岐点であることを改めて示した。今後も業界再編の動きが続く可能性が高く、消費者の支持を得られるブランド戦略と柔軟な経営判断が一層求められそうだ。
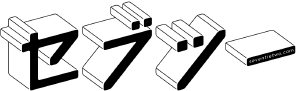


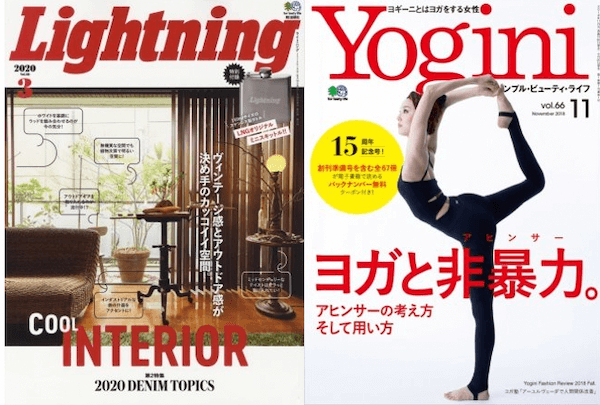


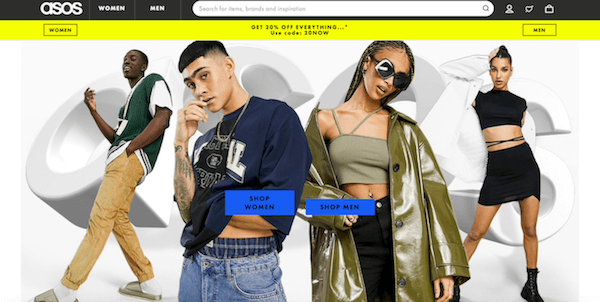










![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)