
2025年、日本のファッション業界において、もっとも大きな存在感を放ったプロダクトのひとつがリカバリーウェアだった。リカバリーウェアとは、着用することで血行促進などを促し、疲労回復をサポートすることを目的とした衣服だ。日本では「一般医療機器」として認められた製品も多く、健康意識の高まりとともに市場は急速に拡大している。
なかでもこの市場をリードしているのが、ワークマンの「メディヒール(MEDIHEAL®)」だ。入荷すれば即完売。昨年は前シーズン比で約10倍となる210万枚を生産したが、それでも在庫は常に逼迫し、異例の売れ行きを記録した。このヒットは偶然ではない。そして短期的なブームで終わらせるつもりもない。そう語るのが、「メディヒール」の開発を担当するワークマンの半田峻也氏だ。半田氏は1994年生まれの31歳。2017年に新卒でワークマンへ入社し、まずは直営店の店長を務めた。その後、2022年に製品開発部へ異動、「メディヒール」を含むものづくりの最前線に立つようになる。
■5年目で訪れた転換点
「メディヒール」は5年前から販売されてきた商品だが、半田氏が開発を担当するようになってから2年後の2024年、状況は一変する。入荷直後から完売が続くようになったのだ。「普段では考えられない売れ方でした。欲しくても買えないお客さまが、明らかにたくさんいました」。こうした状況を受け、ワークマンは大胆な決断を下す。生産量を一気に約10倍、210万枚へと増産した。「正直、前代未聞でした」と半田氏が振り返るように、ワークマンとしても異例の数量だった。ただ、その時点で、「これは大ヒットになるかもしれない」という予感はうっすらと感じていたという。
昨年9月1日に行われたワークマンの展示会を境に、「メディヒール」の動きはさらに加速する。その週末には、1日で約7万点を販売。在庫が安定する間もなく、売れ続ける状況が続いた。他社もリカバリーウェア市場に参入し、販促を重ねる中で、少しずつ認知も積み上がっていった。「これ、という決定打はないと思っています。水が100度に達した瞬間に沸騰するように、あるラインを超えたところで一気に広がりました。それが2024年だったのではないでしょうか」。市場そのものが成熟し、タイミングが重なった結果だった。
一方で、社内では慎重な声もあった。「作りすぎではないか、余るのではないかという意見は当然ありました」。それでも、最終的に大きな反対は起きなかった。現場には「しっかり作って、しっかり供給したい」という共通認識があったからだ。「200万枚作ると決めたなら、みんなで売り切ろうという空気が自然と生まれました」。さらに、この流れを後押ししたのが、武井壮のアンバサダー起用だった。
■「百獣の王」がアンバサダーに
武井壮はテレビやSNSでの高い発信力を持つ一方で、「良いものは良い、ダメなものはダメ」と忖度しない人物として知られている。半田峻也氏が武井壮の名前を思い浮かべたのは、単なる知名度からではなかった。
「10年以上前ですが、武井壮さんが女性タレントと同棲を始める、というテレビ番組の企画がありました。そのとき最初にやったのが、布団のシーツを買いに行くことだったんです。理由は、綿のシーツじゃないとコンディションが下がるから。芸能人でありながらアスリートのような方で、コンディションに対する向き合い方がまったく違うと感じました。だからこそ、この人に“良い”と言ってもらえたら、商品としての信頼性は揺るがないと思いました」。
武井壮は、十種競技で日本チャンピオンに輝いた経歴を持つ。しかも競技を始めてわずか2〜3年で頂点に立った異色の存在だ。その背景には、徹底した自己分析がある。室内の温度や湿度、体温を1日6回測定し、手首や足首、心拍数まで細かく記録する。どの環境に身を置けば自分のパフォーマンスが最大化されるのかを、冷静に数値で把握してきた。
実際、今回のアンバサダー起用は、事前に綿密な「作り込み」をしたものではなかった。「メディヒール」を初めて着用してもらい、その場で率直な感想を聞く、いわばぶっつけ本番だった。「正直、ダメ出しされる可能性もあると思っていました」。だが、返ってきたのは、「今まで着たことがないくらい、着心地がいい」という言葉だった。
忖度のない評価だったからこそ、その一言は重みを持った。武井壮自身もその感想を展示会の場で語り、SNSでも発信。反響は想像以上だった。さらに象徴的だったのが、モンゴル滞在時のエピソードだ。遊牧民とともにゲルで移動する過酷な環境の中で、武井壮は「メディヒール」を着用し続け、その様子をインスタグラムに投稿。ルームウェアという枠を超え、「移動中も着続けられる服」として映し出されたその姿は、プロダクトのリアリティを強く印象づけた。
「気に入っていただけたのが伝わってきて、本当に嬉しかったですね」と半田氏は語る。見た目は極めてベーシックで、パッケージで機能は訴求しているものの、一見して「疲労回復」を想起させる派手さはない。だからこそ、コンディションにこだわる武井壮の実体験が、なによりの説得力を持った。
■「年間2000万枚」と「海外」という次の問い
一方で、リカバリーウェアに対して、「本当に効果があるのか」という懐疑的な声が多いのも事実だ。半田氏は、「むしろ、そういった人たちに届いた感覚があります。1,900円という価格なら、一度試してみるかと手が伸びたのではないでしょうか。ワークマンなら、ちゃんとしたエビデンスがあるだろう、という信頼感も大きかったと思います」。
2026年は「年間2000万枚」を生産し、「国民の5人にひとりが着ている状態」を目標に掲げる。その達成に向け、アイテム数はこれまでの24から30〜40アイテムまで増やす。これまでの主軸であるルームウェアに加え、用途と季節に応じた展開を強化する。春先には、ルームウェアにとどまらず、近所への外出や軽い移動にも対応できるデザインを用意する。5〜6月は、室内の冷房温度には大きなばらつきがあるため、薄手の素材を投入する。
生産体制も見直した。東南アジアに加え、中国にも生産拠点を設け、日本への配送リードタイムを1カ月から2週間へ短縮。国内には最大8000坪の倉庫を用意し、毎月100万点単位で在庫を積み増していく計画を立て、安定供給を優先する。「疲れている人が、誰でも回復できる。そういうインフラとして、メディヒールが役に立てたらと思っています」。
半田氏は、市場の成長を前向きに捉えつつも、冷静な視点を失っていない。「市場が広がるということは、それだけ人々のコンディションが良くなるということ。その価値観自体は、とてもいいことだと思います。ただ、市場が大きくなっても、買える人が限られてしまったら意味がありません」と話す。高価格ゆえに買えない人が生まれる市場は、健全ではないともいう。他社は広告やブランディングに多額のコストをかける。ワークマンは、その分を製品に集中投下する。その構造の違いが、価格差となって現れる。市場の成長は歓迎しつつも、ワークマンは「誰でも手に取れる価格」を崩さない。プレミアムラインなどは現状では考えていない。
2029年にはワークマンとして海外進出を予定しているが、「メディヒール」の海外展開については現時点では慎重だ。日本には「一般医療機器」という枠組みがあり、衣服で疲労回復をうたえる。だが、海外には似た思想の商品はあっても、「リカバリーウェア」として制度的に位置付けられておらず、日常に浸透している例は少ない。この仕組みをどう海外に伝えるかは、今後の課題だ。だが、この分野は、日本ならではの文化になり得ると半田氏は考えている。「衣服で疲労を回復する」というコンセプトを海外に向けてどう伝えていくかは、「メディヒール」にとって次なるチャレンジだろう。
■「日常着」をつくる仕事
半田氏が手がけているのは、「メディヒール」だけにとどまらない。「ワークマンカラーズ」におけるカジュアルウェア全般をマネジメントし、日々、膨大なアイテムと向き合っている。企画の段階では、正解は見えない。これだけ作って、本当に売れるのかという不安は、いつもつきまとう。ハラハラする局面も多く、決して楽な仕事ではない。それでも、売り場で手に取られ、「これ、いいよね」と声をかけられる瞬間がある。「世の中に供給した甲斐があったなと感じますし、それがやりがいでもあります」と、目を細める。
「リカバリー」という言葉が特別な価値として消費されがちな時代に、ワークマンが目指しているのは、あくまで「日常着」だ。「メディヒールも日常着として当たり前の存在になれればと思います」。誰もが手に取れる価格で、必要な人にきちんと行き渡る。その当たり前を成立させるために、今日も膨大な選択と判断を重ねていく。そして、「メディヒール」は今日も誰かの疲れを癒している。

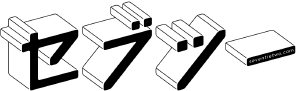











![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)