
三越伊勢丹ホールディングスの今回の決算は静かに強かった。売上高はわずかに控えめになったが、利益はむしろ積み増し、期末配当は30円から35円へ増額。下方修正が相次いだ百貨店の中で、口を開いた瞬間に「増配」を出したのは三越伊勢丹だけだ。
本日の株価は2,512円(11月12日)。特別なニュースがなくても値動きが安定しているのは、中身に理由がある。なぜ売上の伸びが鈍っても利益が出るのか。なぜ1社だけ下方修正を避けられたのか。その答えは、今年の百貨店を分けた「顧客構造」の違いにある。
■利益を落とした百貨店と、落とさなかった三越伊勢丹
今期の百貨店は、訪日客の反動減と高額品の鈍化で利益を落としやすい構造にあった。髙島屋もJ.フロントも、通期で利益を下方修正。売上は上がっているのに、利益はついてこなかった。
ただ、三越伊勢丹だけは違った。売上収益の調整幅はごく小さく、営業利益は据え置き。経常利益と当期利益は上方修正となった。つまり、他社がもっとも崩れた「利益」が落ちなかった。これは珍しい。しかも増配だ。沈黙の理由は、利益構造の強さにあった。
■利益を支えたのは国内の識別顧客だ
利益を出せた理由は、海外でもインバウンドでもなく、国内の識別顧客だ。識別顧客全体は前年比約1割増で伸び、その中でも年間300万円以上の上位ステージが特に強かった。売上を押し上げたのはこの層だ。
10月の売上速報を見ると、全国百貨店計が前年比104.3%だったのに対し、三越伊勢丹計は105.9%。免税が弱い月でも崩れなかった。つまり、誰が買ったのかが利益を決めた。
ここに三越伊勢丹の強さがある。百貨店の利益は客数の多さではなく、名前の分かる顧客の購買額で決まる。その核心となる顧客を、三越伊勢丹はしっかり抱えていたんだ。
■CRMの深さで、百貨店の勝負が決まる
CRMとは「客数を増やす」のではなく「誰が何を買っているのか」を見える化し、その人に合わせて店の動きを変える仕組みだ。百貨店は昔は集客合戦だったが、今は名前の分かる顧客を育てる方が利益になる。
三越伊勢丹は、エムアイカード、アプリMI W、外商の3つが1本の線でつながっている。カードが顧客を見つけ、アプリが接点を増やし、外商が深い関係をつくる。実働レベルでここまで機能している百貨店は他にない。これが「利益が落ちにくい百貨店」を生んでいる。
■投資判断は?
短期は2,450〜2,550円のレンジ。中期は2,600円台を固めるかどうか。配当利回りは約1.3%と高くはなく、景気敏感業種でもある。長期の安定配当株というより、中期で構造変化を読む銘柄だ。巳之助の購買レンジは2,450〜2,550円だな。2,600円台を固めてくれば、一段高の芽が見えてくる。
プロフィール:いづも巳之助
プライム上場企業元役員として、マーケ、デジタル事業、株式担当などを歴任。現在は、中小企業の営業部門取締役。15年前からムリをしない、のんびりとした分散投資を手がけ、保有株式30銘柄で、評価額約1億円。主に生活関連の流通株を得意とする。たまに神社仏閣への祈祷、占い、風水など神頼み!の方法で、保有株高騰を願うフツー感覚の個人投資家。
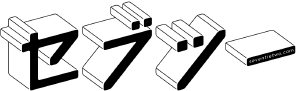










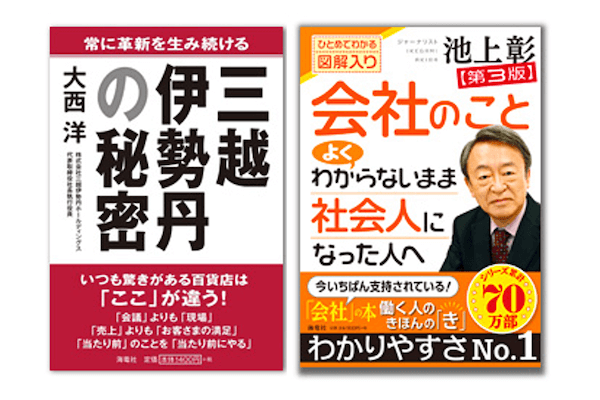
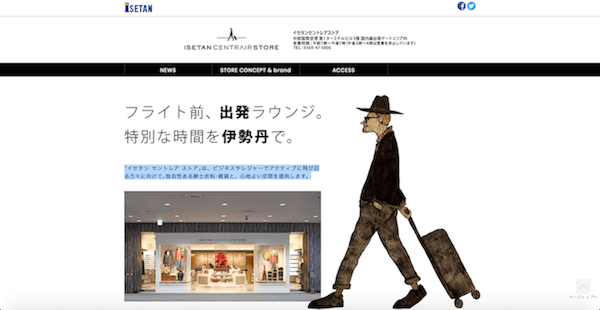
![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)