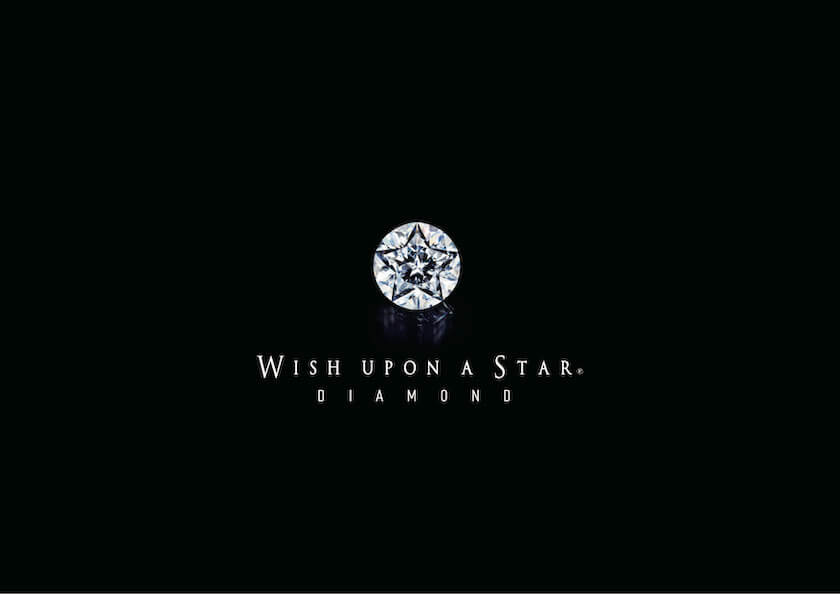
ジュエリーブランドを展開するフェスタリアホールディングスが、2025年8月期決算を発表。売上高94億300万円(+1.0%)、営業利益2億8900万円(+7.0%)と増収増益。Eコマース売上は前年比+30.8%、台湾事業も黒字拡大。株価は500円後半。小粒ながら、地金高騰やインバウンド減少を吸収して利益を積み上げた。巳之助が星に願いをかけたら、「フェスタリアはどうだ?」という声が聞こえたんだ。
■星が売れる理由は、ジュエリーではなく「意味」を売っている
フェスタリアの代名詞は「Wish upon a star」。顕微鏡レベルの精密カットによって、ひとつのダイヤの中に大小二つの星が浮かび上がる。ブランドはこれを「今の自分」と「未来の自分」と名付けた。この構造が、今の若い世代の感性に刺さったんだ。物質的なラグジュアリーではなく、自分のストーリーを象徴するモノが選ばれる時代。「自分に意味がある買い物」を求める消費心理に、フェスタリアの星はぴたりと合った。
■20年前に始めて、なぜ今まで当たらなかったのか?
実はフェスタリアは、20年前からこの「星の物語」を提唱していた。しかし当時はSNSがなく、ブランドの「語り」を可視化できなかった。だからいくら販売員が語っても、それを共有する場がなかったのだ。時代が変わり、InstagramやTikTokが「共感の場」となった。いわば、時代がやっとフェスタリアに追いついたというわけだ。
■数字の裏側──Eコマースと台湾が利益を押し上げた
2025年8月期の売上高は94億300万円、営業利益は2億8900万円。営業利益率3.1%と小さいが、国内外でバランスが取れている。Eコマース売上は+30.8%。コロナ期から約5年で平均客単価が7万円台から9万円台へ上昇した。販売チャネルの強化が成功した理由は、店頭と同じ「体験」をオンラインに移植したこと。星が浮かび上がる瞬間を動画で見せ、購入までの感情体験を再現した。オンラインであっても「共感接客」を失わない設計が、客単価の上昇を支えたね。
■百貨店ブランドとしての足場
フェスタリアは、伊勢丹新宿本店、銀座三越、阪急うめだ本店など全国の主要百貨店に展開。同時に、ららぽーと、ルミネなどのモール業態にも出店している。つまり、百貨店の「贈り物需要」とモールの「自己投資需要」を両方取る構造。この二面性が、フェスタリアを単なるジュエリーブランドではなく「感性型SPA」に押し上げた。
■自社製造だからこそ「1点もの」が叶う
フェスタリアが強い理由のひとつは、ベトナム工場による一貫製造。顧客が石の大きさや地金カラーを指定し、職人がその場で仕上げる仕組みを持つ。いわば、カスタマイズを通じて「自分の星」を作る体験だ。大量生産ではなく、「意味の再現性」を追求する少量SPAモデル。これは、外部委託が主流のツツミやヴァンドーム青山にはできない芸当なんだよ。
■他社との違い──ハイエンドとマスの間にある「共感ブランド」
ジュエリー業界は三層構造だ。ハイエンドブランドは世界観と価格で勝負し、マス(4℃・ツツミ)は販売網と手頃さで勝負する。その中間で、「感性と構造の両立」を実現しているのがフェスタリアだ。百貨店の高級感を保ちながらも、顧客参加型の物語を軸にしている。国内ではこのポジションを取れる企業がほとんどいないね。
■投資判断/適正株購買価格
現在の株価は570円。配当20円に優待1万円相当。実質利回りは約3.8%で、下値リスクは優待が支える構造。業績の伸びしろとアジア展開を考えれば、適正購買レンジは550〜600円。来年3月の中間決算で進捗が見えれば、700円台の見直しが現実的だ。
プロフィール:いづも巳之助
プライム上場企業元役員として、マーケ、デジタル事業、株式担当などを歴任。現在は、中小企業の営業部門取締役。15年前からムリをしない、のんびりとした分散投資を手がけ、保有株式30銘柄で、評価額約1億円。主に生活関連の流通株を得意とする。たまに神社仏閣への祈祷、占い、風水など神頼み!の方法で、保有株高騰を願うフツー感覚の個人投資家。
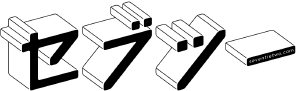




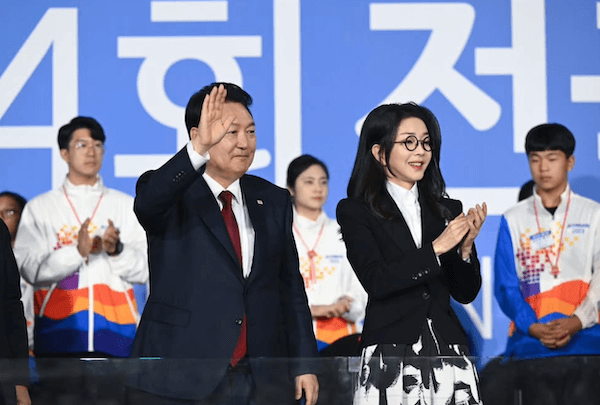













![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)