
おや?大阪・関西万博が終わった大阪が静まるどころか、政治・経済が再びざわつき始めた。エイチ・ツー・オー リテイリング(以下、H2O)の株価は2,078円(10月20日終値)。一見パッとしないが、実はこの企業、万博後に「新しい経済拠点」を動かしている。
■万博が終わっても続く街の再生
2025年春から秋にかけての大阪・関西万博は、観光とインバウンドで街を大いに賑わせた。だがイベントが終われば、一時的な特需の反動が来る。それが通例だ。ところがH2Oは、「万博後の経済をどう動かすか」を最初から計算していたようだ。
10月15日に発表されたニュースでは、同社が保有していた東宝株170万株(約149億円)を売却し、133億円の特別利益を計上予定。さらに、9月の月次売上は前年比+3.9%と堅調。特に博多阪急+34.0%、阪神にしのみや+15.7%と、郊外や地方店が力強い。つまり、H2Oは「イベント依存」ではなく、「生活圏の深掘り」で利益をつなぎ始めているんだ。
■JRが「動線」を売るなら、H2Oは「滞在」を売る
東京ではJR東日本がSuica経済圏を拡大し、「駅ナカ」に人を流すビジネスで成長した。一方の阪急阪神グループ(H2O)は、逆を行く。「動かす経済」から「居る経済」へ。例えば、阪急うめだ本店。延床約10万平方メートルのうち、およそ3割が非物販スペースだ。その中でも「祝祭広場」「うめだスーク」「屋上庭園」など、実際に「モノを売らない体験ゾーン」は全体の約2割を占める。
阪神梅田本店ではさらに進み、非物販比率は約35%、そのうち体験・文化スペースが25%前後。一般的な百貨店では非物販が10%程度だから、H2Oの百貨店は全国平均の約3倍の「居場所」を持つことになる。それが人を留め、購買を誘発する。「立ち寄る」ではなく「居たくなる」その構造こそがH2Oの「大阪モデル」だ。
■数字の裏側にある「滞在経済」の思想
H2Oは、鉄道や不動産を持つ阪急阪神ホールディングスの流通部門。電車を動かさないが、「街の時間を動かす力」を持っている。鉄道を担う阪急電鉄と阪神電気鉄道が人を運び、阪急阪神不動産が街を整え、そしてH2Oリテイリングが「過ごす場所」を編集する。その三位一体の仕組みが、万博後の大阪で再び機能し始めた。
千里中央公園の再整備事業では、H2Oが代表企業としてローソン・NTT西日本と組み、「公園そのものを商業・文化の場に変える」という官民連携を推進。駅前でも公園でも、「滞在」が利益を生む経済モデルを作り出している。
■投資判断
H2Oの業績は、まだ安定成長の途上だ。2025年度上期の連結売上高は前年比+3.9%、営業利益は着実に回復。株価は2,000円台前半で推移しているが、PBRは0.8倍前後と資産に対して割安圏。特別利益による財務改善もあり、自己資本比率は50%超へ。
巳之助の読みでは、適正購買レンジは1,950〜2,100円台だな。東宝株売却による利益計上が一巡し、「滞在型の収益モデル」が実際に業績に反映されるのは2026年春以降。中長期の「大阪モデル」銘柄として拾う価値がある。
巳之助は「一過性の花火」と「息の長い街づくり」で少し迷うけど。
プロフィール:いづも巳之助
プライム上場企業元役員として、マーケ、デジタル事業、株式担当などを歴任。現在は、中小企業の営業部門取締役。15年前からムリをしない、のんびりとした分散投資を手がけ、保有株式30銘柄で、評価額約1億円。主に生活関連の流通株を得意とする。たまに神社仏閣への祈祷、占い、風水など神頼み!の方法で、保有株高騰を願うフツー感覚の個人投資家。
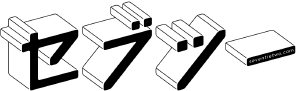
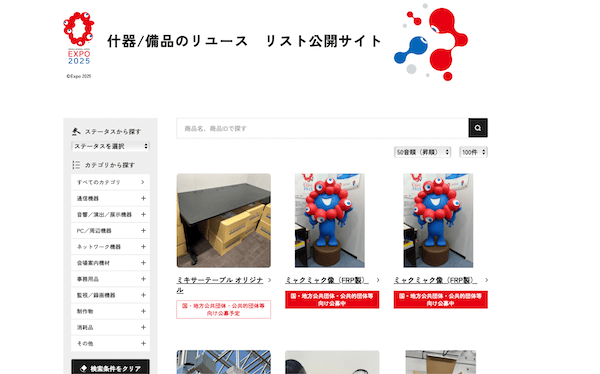
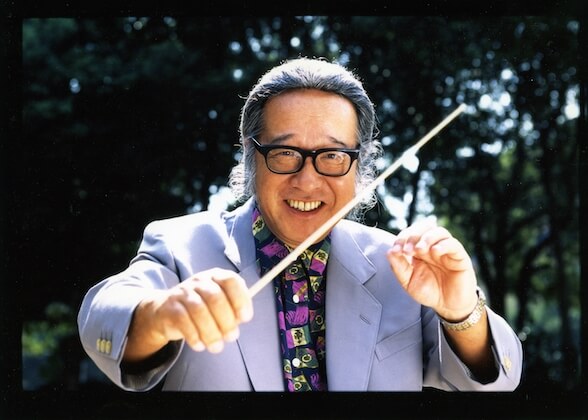







![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)