
新年2023年もいよいよ本格的に動き出した。年末年始の10日間ほどの休暇をYouTube浸けという感じで政治、経済番組を見続けていた。楽天の倒産危機ネタとソフトバンクグループ倒産危機ネタがやたら多かった。楽天の倒産危機は、モバイル事業が赤字をタレ流していることが最大の原因だ。楽天証券、楽天銀行の上場で新規資金獲得という手がまだ残っているが、それでモバイル事業が黒字化するわけではない。手っ取り早いのはモバイル事業に見切りをつけることだが、そうなれば創業者の三木谷浩史社長の進退問題に発展するのだろう。
小さい話だが、アマゾンに代わって2019年10月開催から楽天をメインスポンサーにしている東京ファッションウィークの行方も気になるところである。
この楽天に比べれば、まだソフトバンクグループにはいろいろと方策がありそうに思うが予断は許されない。
楽天とソフトバンクグループが話題を独占している観のある年末年始の経済界だが、年初から悪いニュースが飛び込んできているのが気になる。
まず東証プライム上場の外食チェーンの第2位(第1位はゼンショーホールディングス、第3位は日本マクドナルドホールディングス)のすかいらーくホールディングスは1月12日に2022年12月期決算の下方修正を発表した。
・売上高:3120億円→3040億円
・営業利益:5億円→−60億円
・経常利益:−20億円→−65億円
・年間配当:12円→0円
コロナ禍長期化やインフレに伴う消費者の生活防衛意識の高まりなどを下方修正の原因に挙げている。コロナ禍の長期化は必ずしも当たっているとは思わないが、見逃せないのは「インフレ進行による生活防衛意識の高まり」という文言だろう。この生活防衛意識という新型ウイルスが特に外食産業を直撃しているようだ。外食産業ばかりでなく、この「生活防衛という新型ウイルス」はあらゆる小売市場に蔓延するのではないか。コロナに匹敵する悪者である。
続いてダイソーに次ぐ100円ショップ業界第3位のキャンドゥが同じ1月12日に2023年2月期決算の下方修正を行った。
・売上高:962億円→927億円(前期実績731億3000万円)
・営業利益:12億4000万円→3億7500万円(同9億6400万円)
・純利益:2億3500万円→−4億6000万円(同1億9400万円)
コロナ特需の反動、円安進行による商品減価率の上昇や水道光熱費の増加などを下方修正の原因に挙げている。
新型コロナウイルス禍で売り上げが減少した企業に実質無利子・無担保で融資する「ゼロゼロ融資」が零細企業や個人事業主(最大融資額6000万円)、中小企業(最大融資額3億円)を助けて来た。その融資額は政府系、民間金融機関も合わせて2021年4月末で約56兆円に達した。日本の国家予算の半分以上の金額だ。これがコロナ禍でも意外なほど倒産が少なかった原因と言われている。
ゼロゼロ融資の実質無利子とは最初の3年間だけ。元本返済は最大5年間猶予されるが、融資が最初期だった企業では今年5月から早くも利払いが始まる。これが特に中小企業と金融機関にとっては新たな「火種」になると言われている。これを見越し悲観した中小企業の倒産が予想されている。
ゼロゼロ融資と関連があるのかどうか、ファッション&アパレル業界でのコロナ禍での倒産は信じられないほど少なかった。ひっそり廃業している小規模な専門店やメーカーはかなりの数に上るのだろうが、昨年末から年初にかけてこの業界の倒産が目に付くようになっている。
そうした中で最大の話題は、岩手県盛岡市に本拠を置く百貨店の川徳(1866年創業)が、12月29日付で岩手県中小企業活性化協議会の支援による事業再生計画を成立させたことだろう。再建に向けて経営体制を刷新新するという。主力取引銀行の岩手銀行などの金融機関や民間ファンド「ルネッサンスキャピタル」の支援により専門人材の外部登用や組織のスリム化を進める。これによる岩手銀行の取立不能または取立遅延の債権は約42億2000万円に上る。郊外のショッピングセンターとの競合に敗れ、コロナ禍でトドメを刺された末の実質的な倒産だが、再建はイバラの道になりそうだ。
新年入りした1月10日には、東証スタンダード上場の紳士服チェーンのタカキューが人員削減の実施を明らかにした。詳細は労働組合と協議後に確定する。同社は2022年2月期に8億7600万円の債務超過に陥り、2024年2月29日までに債務超過を解消できなければ上場廃止になる。その廃止を免れるための今回のリストラだ。同社は2020年2月期から2022年2月期までの3期中に全店舗の約45%に当たる136店舗の退店を実施している。一世を風靡した紳士服チェーンもいよいよ土俵際に追い詰められた。
楽天、ソフトバンクグループ、インフレ進行下の生活防衛という新型ウイルス、ゼロゼロ融資返済開始などなど日本経済は火種満載である。これに危機をはらんだ国際情勢、混迷する国内政局が加わるのだから本当に大変な年になりそうである。
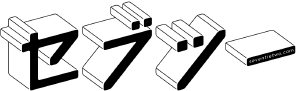


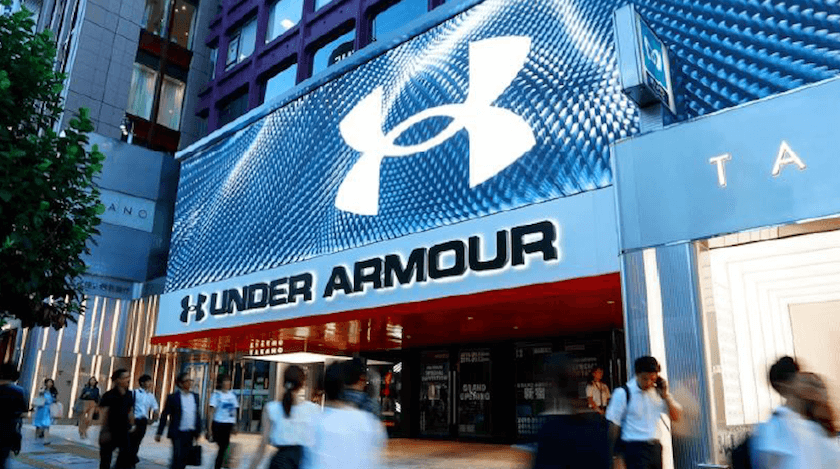

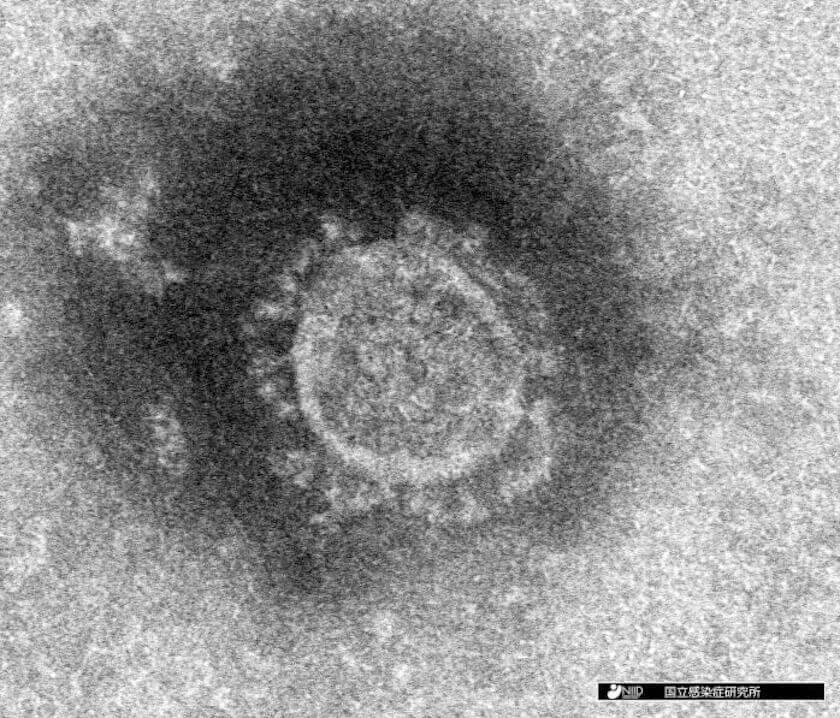















![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)